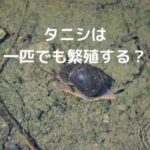メダカとタニシの混泳!タニシはメダカを食べる⁈メダカの卵の守り方

タニシはメダカを食べるのか?
メダカの卵をタニシは食べる?
タニシの食べ物はなに?
タニシとメダカは混泳できる?メリットとデメリットは?
こんなタニシの食べ物とメダカの捕食についてご紹介いたします。
[toc]
タニシはメダカを襲う?
水槽のコケ取りのためやビオトープの同居人としてタニシを飼育していたら、メダカを食べたなどという事例があるようですが、タニシは本当にメダカを食べるのでしょうか?
メダカがタニシに食べられてしまうということはタニシがメダカを襲うのか?
そんな疑問から解決していきましょう。
まず、結論から言えばタニシがメダカを襲うことはありません。
タニシは攻撃的なハサミを持つわけでもなく、鋭い歯を持つわけでもありせん。
貝の中には毒矢のようなものを魚に刺して麻痺させるものもいますが、タニシにはそのような武器もありません。
よってメダカを襲う(捕らえる)ことはタニシには出来ないのです。
では何故タニシがメダカを食べたなどという事例があるのでしょうか。
そこにはタニシの食物が関係しています。
タニシはメダカを食べるのか?タニシの食べ物
タニシがメダカを襲うかについては否ですが、タニシがメダカを食べるかについては否ではないのです。
その理由をタニシの口の仕組みや食べ物の話から説明していきましょう。
タニシの口には薄く細かい歯がたくさん並んだ歯舌という食べ物をかじりとる器官があります。
タニシの歯は中央に中歯、両側部に側歯と縁歯があり、いずれもヘラ状で薄く柔らかいので細かい藻類や泥の中の有機物を掻き取るように食べます。
さらに呼吸器官であるエラは一方で摂食器官にもなっており、絡みついた水中の有機物を餌として取り込むように食べます。
このことだけ聞くとメダカなんて食べないじゃんと思われるかもしれませんが、メダカがもし死んでしまって腐敗が始まれば、メダカも一つの有機物になるのです。
生物が死ぬとその生物を分解し、食べる生物が現れるのはどの世界でもあることです。
それが他の動物であったり、昆虫であったり、もっと小さな微生物であったりと。
水中ではその生態系の一部にタニシが含まれており、タニシは水中の生物の死骸(有機物)を食べ、分解しているのです。
よって生きているメダカを襲って食べるようなことは無くても、死んでしまって腐敗が始まったようなメダカであれば、十分食べる可能性はあるということになります。
さらに近年では、熱帯性のジャンボタニシと呼ばれるリンゴガイ科の貝類がタニシと間違われて飼育されることもあります。
ジャンボタニシは日本の在来種よりも強靭な歯を持ち、タニシがまだ手をつけないようなものでも、かじりとるように食べるという報告もあります。
もし、ジャンボタニシを飼育しているのであれば、通常のタニシ以上にメダカを食べる可能性は高まると言えるでしょう。
今までの話をまとめるとタニシはメダカを襲うわけではなく、水槽の掃除屋としての役割を担っていると言えるのです。
よってタニシとメダカの混泳は問題ありません。
ただ、全くデメリットがない訳でもありませんのでタニシとメダカの混泳に対するメリット・デメリットも書いておきます。
タニシとメダカの水槽混泳メリット・デメリット
タニシとメダカの混泳は可能ですが、双方を混泳させることによるメリットとは何なのでしょうか?
また、混泳によるデメリットはあるのでしょうか?
まず、メリットとしてはタニシの持つ水質浄化能力です。
タニシは先にも記載しましたように水槽内の有機物を食べて分解します。
よってメダカのエサの食べ残しや糞などを分解し、微生物が食べやすいものへと変えていきます。
タニシを水槽やビオトープに入れておくことによって有機物が減り、水の腐敗や水質の悪化を抑制する効果が見込めるのです。
また、水槽内のコケなども食べますので、コケ取り生体としても活躍してくれます。
このようなことを聞くとタニシの存在は至れり尽くせりのように見えますが、あくまでもタニシは生態系のサイクルの一部を担っていることは忘れないでください。
そのことを忘れて生態系のバランスを崩してしまうとタニシを入れることがデメリットにもなりかねません。
事例を挙げると、タニシの水質浄化能力を過信し過ぎて水槽の水換えをサボったり、エサを沢山与え過ぎたりしてしまうことです。
確かにタニシには水質浄化をする力がありますが、水槽の水質は管理者がしっかり管理することが前提となります。
他にもタニシがコケ取りや水質浄化に良いと聞き、過剰な数のタニシを水槽内に入れてしまうと今度はタニシの糞が増えすぎたり、餌不足に陥ったりと違った問題も出てきてしまいます。
あくまでもメダカの数、タニシの数、バクテリアの繁殖具合、水槽の大きさなど色々な飼育条件を加味したうえでバランスの取れた混泳を心がけることが大切です。
メダカの稚魚(赤ちゃん)と卵を守る
最後にタニシを水槽に入れる際のメダカの繁殖についても触れておきます。
タニシはメダカを襲うことはないという話をしましたが、メダカの卵については不明な点も多いところです。
完全な草食生物で無い限り、口に入るものであれば食べる可能性はあるのが生物本来の姿です。
よってメダカの卵や弱弱しい生まれたばかりの稚魚などは捕食対象となる可能性もあります。
メダカの繁殖率を高めたいのであれば卵や稚魚はタニシと隔離することをお勧めします。
ただ、繁殖の話になるとタニシ以上に親メダカのほうが卵や稚魚を食べてしまうことが多いのでタニシの存在に関係なく必然的に隔離は行われているはずです。
もしくは自然の環境に似せたビオトープなどでは、自然の摂理に任せて淘汰されるものは淘汰されるまま、その中を生き延びたものだけを育てるという方法もあるかもしれません。
ちなみにメダカに限らず稚魚や卵を親魚から隔離する方法として産卵箱などが安価で販売されていますので、うまく利用することで別の水槽を用意する経費や手間などが省けます。

タニシとメダカの混泳まとめ
- タニシがメダカを襲って食べることはない。
- タニシは生物の分解者であるため死んだメダカや弱ったメダカは食べる。
- タニシには水質浄化能力があるため混泳させることにはメリットがある。
- 何事にも生態系のバランスは大切。
今回はメダカとタニシの混泳についてご紹介しました。皆様のアクアリウムライフの参考にしていただけると幸いです。
合わせて読みたい関連おすすめ記事
-

-
タニシ?水草水槽に小さな貝(スネール)が大量発生 増える理由とスネール駆除
タニシ?水草水槽に小さな貝(スネール)が大量発生 増える理由とスネール駆除 水草水槽にいつの間にか自然と現れる小さな貝(snail)。 スネールやスネイルなどと呼ばれ水草水槽などのアクアリウムでは駆除 ...
続きを見る
-

-
スネールの卵は孵化前に駆除!卵の孵化日数と駆除方法
スネールの卵は孵化前に駆除!卵の孵化日数と駆除方法 水槽にスネールの卵!どうしたら良いのか? タニシのような貝の卵を駆除したい。 スネールの卵の孵化日数はどのくらい? スネールの卵を駆除する方法は? ...
続きを見る
-

-
タニシの卵!? ピンク色や透明の卵はタニシではない!?それならメダカの卵?
タニシの卵!? ピンク色や透明の卵はタニシではない!?それならメダカの卵? メダカの卵とタニシの卵の違いや見分け方を知りたい。 田んぼで見かけるピンク色の卵はタニシの卵? ジャンボタニシの卵には毒があ ...
続きを見る
-

-
タニシの種類と見分け方 スネールにジャンボタニシ・オスメスの違いは?
タニシの種類と見分け方 スネールやジャンボタニシとの違い タニシの種類を知りたい。 タニシとスネールの違いを知りたい。 タニシに似たジャンボタニシとは? ジャンボタニシとタニシの見分け方を知りたい。 ...
続きを見る
-

-
タニシは一匹でも繁殖する?タニシの繁殖と水槽に現れるタニシに似た貝類との違い
タニシは一匹でも繁殖する?タニシの繁殖と水槽に現れるタニシに似た貝類との違い タニシは一匹でも繁殖するのか? 水槽に現れるタニシに似た貝類の繁殖は? 水槽のタニシもどき(スネール)の繁殖を防ぐ方法は? ...
続きを見る
-

-
タニシの卵とジャンボタニシの卵・メダカの卵それぞれの違いと特徴
タニシの卵とジャンボタニシの卵・メダカの卵それぞれの違いと特徴 タニシの卵とは?画像や写真で見てみたい。 ジャンボタニシの卵とは? タニシの卵には毒がある? 水槽で見かける透明な卵はタニシの卵? タニ ...
続きを見る
-

-
タニシの水質浄化効果と水槽掃除の関係!水槽掃除が減らせる?
タニシの水質浄化効果と水槽掃除の関係!水槽掃除が減らせる? タニシには水質浄化能力がある?その効果は? タニシは水槽を掃除してくれる? タニシを入れておくと水槽掃除の頻度を減らせる? タニシを水槽に入 ...
続きを見る
-

-
タニシの餌は何?キャベツなどの野菜や昆布なども餌になる?
タニシの餌は何?キャベツなどの野菜や昆布なども餌になる? タニシの餌には何を与えればいい? タニシの餌にキャベツなどの野菜を与えても大丈夫? タニシは昆布やワカメを餌として食べる? タニシの餌にカルシ ...
続きを見る